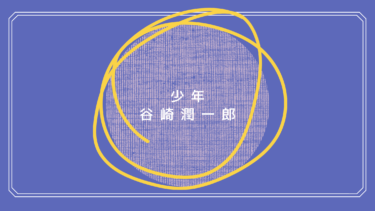『痴人の愛』は、震災前の東京と横浜を舞台にしている。この時代は、日本でも一般の人々に欧米の生活様式が浸透し始め、活動写真やカフェエ、ダンスホールが出現し、モボ(モダンボーイ)やモガ(モダンガール)と呼ばれた、西洋文化の影響を受けた流行の最先端をゆく若者が街に進出した時代である。
このような時代背景の中、『痴人の愛』は当時の若者の関心を集め、登場人物のナオミにちなんで「ナオミズム」という流行語が生まれるほど社会的な反響を呼んだようだ。
当然、この『痴人の愛』にも当時の風俗は色濃く描かれており、登場人物たちは活動小屋に行き、カフェエに行き、ダンスホールに行き、と時代を謳歌している。
あらすじ
物語のあらすじは以下の通りである。
「草深い百姓家」出身のサラリーマン譲治が、カフェで働くナオミを引き取るものの、ナオミは次第に我儘な性格を現し、数人の男と関係を持つなど娼婦性を発揮していく。裏切られた譲治はナオミを追い出すものの、間もなくよりを戻すと、ナオミの我儘と浮気を全て受け入れて隷属する。
最後に、物語は「私自身は、ナオミに惚れているのですから、どう思われても仕方がありません。」という主人公譲二の言葉で終わる。
感想
『痴人の愛』で面白いのは、主人公譲治が自分のことを愚かだと認めながらも、最後にこのような形で開き直っている点にある。つまり、「ナオミのようなふしだらな女と付き合うべきではない」といった常識人の批判も、「どう思われても仕方がありません。」の返答で一蹴されてしまうのだ。このようにして、主人公譲治とナオミの二人の世界は、あらゆる外部の批判から解放されている。
そして、主人公譲治のこの最後の言葉を前に、作者は読者に問いかけるのである。
ナオミのような悪女の魅力に嵌ることは、世間的にみれば愚かな行為に見えるかもしれないが、そこに陶酔の喜びがあるならば、主人公譲治のことを誰も批判することはできないのではないか、と。この点から見ても、『痴人の愛』が三人称ではなく、一人称の物語である重要性があるように思える。
同じようなことが、『痴人の愛』に描かれている登場人物たちの西洋崇拝についても言える。登場人物たちは、実際の西洋を見たことはないはずである。そのため、例えば主人公譲治が思い描く西洋のイメージとは、映画のスクリーンを通した実体無きイメージに憧れを抱くようなものであったかもしれない。ただ、そのような西洋崇拝の形であれ、憧れの西洋に近づいていく高揚感に浸れるのであれば、それはそれで幸せだろう。
なお、谷崎が24歳の時に書いた処女作『刺青』の初めの一文を見ると、「それはまだ人々が「愚」と云う貴い徳を持って居て」とある。『刺青』で言及されているこの「愚」と、『痴人の愛』の「痴」は、同一の主題の上にあるように思える。
一貫して、「愚」や「痴」の思想の上に成り立った谷崎の文学・思想は、他の文学者たちの思想に大きな影響を与えた第二次世界大戦における日本敗戦も例外でなかった。
谷崎文学の最大の理解者の一人であった三島由紀夫の言葉を借りると、谷崎にとって日本の敗戦とは、「日本の男が白人の男に敗れたと認識してガッカリしているときに、この人(谷崎)一人は、日本の男が、巨大な乳房と巨大な尻を持った白人の女に敗れた、という喜ばしい官能的構図」ということなのだそうだ。
『痴人の愛』で見られる、主人公譲治のナオミへの服従は一見愚行に思えるものの、譲治がその愚行への覚悟を決めて陶酔に酔いしれる時、それを美徳として肯定できるものとして描いている。その姿は、戦時中に『細雪』を執筆していた谷崎の姿に重なるようにも思える。
ブログの更新情報をメールでお知らせします。
ぜひご登録ください!