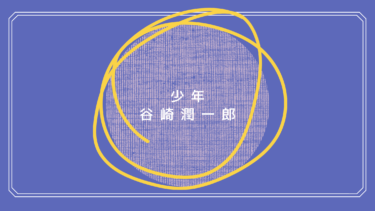『刺青』は、明治43年(1910年)に24歳の谷崎潤一郎が発表した処女作である。
あらすじ
江戸の刺青師清吉は、理想の美女に自分の刺青を刺り込むという宿願を抱いていた。願いを抱いてから4年目、理想の足を持つ女性を見つける。翌年、偶然その女性と再会し、女性の背中に巨大な女郎蜘蛛を刺った。清吉は刺青に己の魂をうち込んだ後、美しくなった女の「肥料(こやし)」となるのだった。
「愚(おろか)」と云う貴い徳
『刺青』は以下の一文から始まる。
其れはまだ人々が「愚」と云う貴い徳を持って居て、世の中が今のように激しく軋み合わない時分であった。
『刺青』
この一文からいくつか分かることがある。
まず初めに、「其れは~時分であった。」とあることから、明治時代から江戸時代を回顧しているという点。二つ目に、「まだ人々が「愚」と云う貴い徳を持って居て」とあることから、今(明治時代)の人々は「愚」と云う貴い徳を持っていない(と筆者が感じている)点である。
つまり、明治の文明開化により、人々が「賢く」なってしまい、「愚」という貴い徳を失ってしまった、と述べている。
当時の芝居でも草双紙でも、すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった。
『刺青』
これは、最初の一文と同じ段落の文章である。ここでは、昔は強者と弱者は美しいかどうかで全て決まっており、「美」が唯一の価値観・尺度であったと語っている。
つまり、『刺青』は、「愚」という徳を失った明治時代の「賢い」人々や、不道徳な「美」を肯定しない一般社会の価値観への挑戦なのである。これは後の作品である『痴人の愛』でも見られるテーマである。
確かな拠り所としての「美」への渇望は、大正3年に発表された『饒太郎』の以下の一文にも表れている。
若しも此のからっぽな世の中に真実らしいもの、せめて真実に近い値のある物が存在するとしたら、「それは美である。」と饒太郎は答えるかも知れない。
『饒太郎』
世の中はからっぽのように思えるが、その中で「美」は確かな真実に近い物であると述べている。
では、谷崎が求める「美」とは何だろうか。その一つは疑いようもなく、女性の足だろう。
女性の足への執着
処女作『刺青』において既に、谷崎の女性の足に対する強いこだわりが見られる。
江戸の刺青師清吉の宿願は「光輝ある美女の肌を得て、それへ己れの魂を刺り込む事」であった。
そして、その美女については色々と注文があり、「啻に美しい顔、美しい肌とのみでは、彼は中々満足する事が出来なかった」のである。
では、どんな美女であればよいのであろうか。彼は願いを抱いてから4年目、ついに理想の女性を見つける。
彼はふと門口に待って居る駕籠の簾のかげから、真っ白な女の素足のこぼれて居るのに気がついた。鋭い彼の眼には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼に取っては貴き肉の宝玉であった。
『刺青』
なんと、女性の足だけから、4年間探していた理想の女性を見つけるのである。
その翌年、同じ女性と再会した際も、「巧緻な素足を仔細」に眺めて、同じ女性だと識別している。感服せざるを得ない能力である。
彼が再会した女性にかける言葉も、「足かけ」という言葉が「足」に掛かっているのが面白い。
丁度これで足かけ五年、己はお前を待って居た。顔を見るのは始めてだが、お前の足にはおぼえがある。
『刺青』
その後も、「若い女が桜の幹へ身を倚せて、足下に累々と斃れて居る多くの男たちの屍骸を見つめて居る」や「真っ白な足の裏が二つ、その面へ映って居た」と、足への愛はとどまる事を知らない。
なお、『刺青』は短い作品ではあるものの、「足」という字が13回登場する(満足の「足」を除く)。
後の谷崎の作品『痴人の愛』や『瘋癲老人日記』にも見られる「女性の足」へのこだわりが、24歳の処女作にして存分に表れているのである。
ブログの更新情報をメールでお知らせします。
ぜひご登録ください!
 Copyright secured by Digiprove © 2020
Copyright secured by Digiprove © 2020