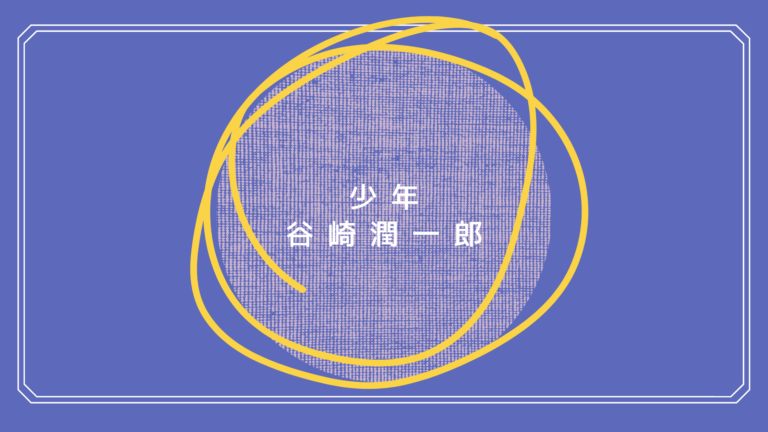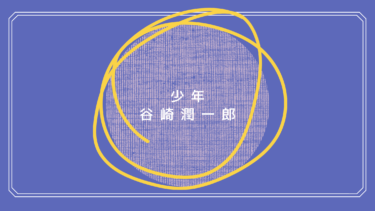1911年に発表した『少年』は、谷崎自身が前期作品の中で「一番きずのない、完成されたもの」と表現し、永井荷風や森鴎外、上田敏にも認められた作品である。
あらすじ
ある時、学校では弱虫な信一の家に、主人公が遊びに行く。家の中での信一は、学校の様子とはうって変わった暴君で、餓鬼大将である仙吉や姉の光子をいじめて遊んでいた。ある夜、光子がいつもピアノを弾いていた西洋館へと忍び込んだ主人公と仙吉は、妖艶な光子の前にひれ伏す。その翌日から、主人公と仙吉は光子の家来になり、最終的には信一も光子の奴隷となっていく。
『少年』の三つの世界と登場人物
『少年』は、登場する三つの世界において、登場人物の立場が変わる点が特徴の一つである。
三つの世界
- 学校を中心とする現実世界
- 塙家の日本館
- 塙家の西洋館
登場人物
- 私(萩原の栄ちゃん):『少年』の語り手。
- 仙吉:名代の餓鬼大将で、学校を中心とする現実世界の中心人物。
- 信一:本妻の子。学校という現実世界では弱虫。塙家の日本館では暴君となり、仙吉との立場は逆転する。
- 光子:妾の子。西洋館の主。最終的には、少年達の国の女王となる。
感想
社会や文化の形態の分け方については、父親を手本とする権威的なパトリズム(父性制)と、母親を手本とする母性愛に満ちたマトリズム(母性制)という概念がある。
『少年』が執筆された明治社会は、近代化が進む典型的なパトリズム社会で、森鴎外や夏目漱石の文学もパトリズム社会で生み出された文学であった。
一方、谷崎はマトリズムを志向した作家で、『刺青』や『痴人の愛』などにもこの傾向はよく表れている。
学校という現実社会では一番力の強い仙吉だが、塙家の内部では信一と立場が逆転する。更に、最終的には、本妻の長男である信一ではなく、妾の子で且つ女性である光子が少年たちの支配者となる。つまり、『少年』では、権威主義的な父性制が、光子という母性制の前に屈する構図になっている。
但し、『少年』において「光子=西洋館=母性制」という構図になっているものの、当時の西洋はマトリズム社会ではない。
西洋渡航の経験がなかった作家の中では、このような誤解が多く見られたようだ。
「西洋館=母性制」という構図は、目の前の現実(父性制)から遠く離れた存在(母性制)として、それを西洋的なものに見出そうとしていただけなのかもしれない。
ブログの更新情報をメールでお知らせします。
ぜひご登録ください!
 Copyright secured by Digiprove © 2020
Copyright secured by Digiprove © 2020